�N���ɌW�邻�̑��̎���
1�@�x���J�n
�@�ސE�N���́A�ސE�������̗������狋�t���R�̂Ȃ��Ȃ������܂ł̕����x�����܂��B
2�@�N��ɂ��x����~
�@�ސE�N���́A���i�Ă��Ă��x���J�n�N��i65�j�ɒB���錎�܂ł͎x������~����܂����A �A�E�������Ɛ��N�����ɂ��65�ɒB����O�Ɏx�������o�ߑ[�u�����̂Ƃ���݂����Ă��܂��B
�A�E���F���a61�N3��31���ȑO
�x���J�n�N��F55��
�A�E���F���a61�N4��1���`����7�N3��31��
�x���J�n�N��F60��
�A�E���F����7�N4��1���Ȍ�
���N�����F���a20�N4��1���ȑO�@�x���J�n�N��F62��
���N�����F���a20�N4��2���`���a22�N4��1���@�x���J�n�N��F63��
���N�����F���a22�N4��2���`���a24�N4��1���@�x���J�n�N��F64��
���N�����F���a24�N4��2���Ȍ�@�x���J�n�N��F65��
��65�Ζ����ł����Ă��A�����@�ʕ\��ꍆ�\�m��ɒ�߂�d�x��Q�̏�ԂɂȂ����Ƃ��ɂ͑ސE�N�����x������܂��B
3�@�ďA�E�ɂ��x����~
�ސE�N���҂̕����s���{���c��c���ɍďA�E�����Ƃ��́A�ďA�E�������̗�������N���̎x������~����܂��B�ߋ��̍ݐE�ƈقȂ�s���{���c��c���ɍďA�E�����ꍇ�����l�ł��B
�Ȃ��A�s���{���c��c�����ω�̑ސE�N���҂�����c���A�m���A�s���A�s�c��c���A�����c��c���ɏA�E����Ă��ސE�N���̍ďA�E�ɂ���~�ɂ͊Y�����܂���B
4�@�����ɉ������ސE�N���̎x����~
�@�ސE�N�������邱�ƂƂȂ����N�̗��N���疈�N�A�O�N�̏������������{���܂��B�ސE�N���̔N�z�ƑO�N�̏������z(�Z���ł̉ېő��������z�x�[�X)���������ꍇ�ɁA�ސE�N���̈ꕔ���͑S�����x����~�ƂȂ�ꍇ������܂��B
�@��̓I�ɂ͑ސE�N���̔N�z�ƑO�N�̉ېő��������z�̍��v�z����700���~���T�����ē������z��2����1���悶�ē����z����~����܂��B�������A�v�Z�̌��ʁA�x����~�z���ސE�N���̎x���z���������Ƃ��́A�ސE�N���̎x���z�̋��z���x����~�ƂȂ�܂�(�@������4���2��)�B
�@�O�N�̏��������ɂ��ẮA���N6���ɑS�Ă̑ސE�N���̎҂ɑ��čs���A�ꕔ�x����~�́A���̔N��6�����痂�N��5���܂ł̊��ԕ��ɂ��čs���܂��B
�@�Ȃ��A�����̔N��1���Ȍ�ɑސE�����҂ɂ��ẮA���̔N�̒����͍s���܂���(���{�s�ߑ�69����2��2��)�B
(1) �O�N�̉ېő��������z
�@���z�����ɂ���~�z���Z�o����ۂ̑O�N�̉ېő������������z�ɂ��ẮA�@�O�N�ɖ{���x�����ꂽ�ސE�N���A�A�O�N�̒n�������@��203���ɋK�肷��c����V�A��p�ُ��y�ъ����蓖�y�ѓ��@203����2�ɋK�肷���V�y�є�p�ُ��ɌW�鏊���������A�n���Ŗ@�̉ېő��������z�̌v�Z�Ɋւ���K��ɂ��������ĎZ�o���܂��B
�@���������āA�O�N�̉ېő��������z�Ƃ́A���^�A���q�A�z���Ȃǂ̏����̍��v�ł��鑍�������珊���T��������̋��z���w���܂��B�Ȃ��A�����ېłƂȂ���̂͏����܂��B
(2) �x����~�z
�@�x����~�z�ɂ��ẮA�{���x������ސE�N���z�ƑO�N�̑ސE�N�����������Z���ł̉ېő��������z�̍��v�z����700���~���T�������c�z��1/2�ƂȂ�܂��B
�O�N�̑ސE�N���E�E�E�O�N�ɓs���{���c��c�����ω������ސE�N��
�O�N�̋c����V�E�E�E�O�N�ɓs���{���c��c���Ƃ��Ď����c����V��
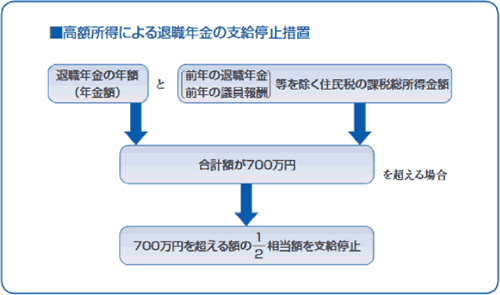
(3) �x����~�̗�
�@�O�N�̏������z�ɉ����āA(1)�N���z���S�z�x����~�̏ꍇ�A(2)�N���z���ꕔ�x����~�̏ꍇ�A(3)�N���z���x����~�ƂȂ�Ȃ��ꍇ�̌v�Z��ɂ��ẮA�ȉ��̂Ƃ���ł��B
�y��1�z�N���z���S�z�x����~�̏ꍇ
- �ސE�N���̔N�z 100���~
- �O�N�̑ސE�N�����������������z 800���~
- 1��2�̍��v�z 900���~
�@�ސE�N���̔N�z(1�D)�ƑO�N�̑ސE�N�����������������z(2�D)�̍��v(3�D)��700���~�������Ă��邽�߁A700���~������z200���~��2����1�̊z100���~���x����~�ƂȂ�܂��B
�@�ސE�N���́A100���~�S�z���x����~�ƂȂ�܂��B
�y��2�z�N���z���ꕔ�x����~�̏ꍇ
- �ސE�N���̔N�z 100���~
- �O�N�̑ސE�N�����������������z 700���~
- 1��2�̍��v�z 800���~
�@�ސE�N���̔N�z(1�D)�ƑO�N�̑ސE�N�����������������z(2�D)�̍��v(3�D)��700���~�������Ă��邽�߁A700���~������z100���~��2����1�̊z50���~���x����~�ƂȂ�܂��B
�@�ސE�N���́A50���~���x����~�ƂȂ�܂��B
�y��3�z�N���z���x����~�ƂȂ�Ȃ��ꍇ
- �ސE�N���̔N�z 100���~
- �O�N�̑ސE�N�����������������z 590���~
- 1��2�̍��v�z 690���~
�@�ސE�N���̔N�z(1�D)�ƑO�N�̑ސE�N�����������������z(2�D)�̍��v(3�D)��700���~��������Ă��邽�߁A�x����~�ƂȂ�܂���B
�@�ސE�N���́A�S�z�x���ƂȂ�܂��B
5�@���t�̐���
�@�c���������͋c���ł����������S�Y�ȏ�̌Y�ɏ�����ꂽ�ꍇ�A�܂��͋c����������ꂽ�ꍇ�́A����Ȍ�A�c���ł������ݐE���ԂɌW��ސE�N���̑S���܂��͈ꕔ�̎x������~����܂�(���@��164����3��1��)�B
�@�܂��A�⑰���t���錠����L��������S�Y�ȏ�̌Y�ɏ�����ꂽ�ꍇ�́A�⑰���t�̈ꕔ���x�����Ȃ����ƂƂȂ��Ă��܂�(���@��164����3��2��)�B
(1) �S�Y�ȏ�̌Y�ɏ��������Y�̏ꍇ
�@�Y�̊m�肵�����̗�������Y���I���̌��܂Ŏx�����~(���@��164����3��3��)���A�Y���I���̗�������͋��t���z��100����20�̊z�������Ďx�����܂�(���{�s�ߑ�70���1���A��2��)�B
�@�Ȃ��A�Y�ɏ�����ꂽ�ސE�N���҂����S���A�芼�ŋK�肷��⑰������ꍇ�́A�Y�̌��ʂ͈�g�ꑮ�ň⑰�ɂ܂ŋy�Ȃ����Ƃ���A�Y����O�̔N���z����ɎZ�肵���⑰�N�����S�z�x������܂��B

�@�����Y��������̒�~�͊܂܂�܂���B
�@��x�c���ɂȂ����҂����Y�����������ƁA�Ăыc�����I�����ꍇ�ł��Y�̌��ʂ͈��������A�����̑ΏۂƂȂ�܂��B
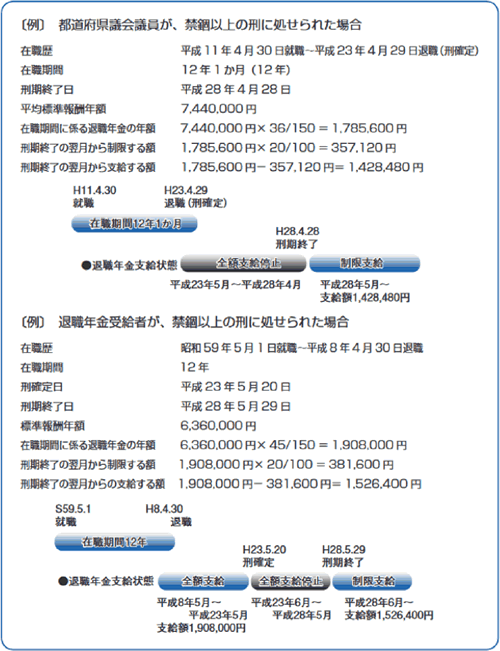
(2) �S�Y�ȏ�̌Y�ɏ������Y�̎��s���P�\���ꂽ�ꍇ
�@�Y�̎��s�P�\�̌��n�������Ƃ��́A�Y�̎��s�P�\���Ԓ����t���z��100����20�̊z�𐧌����܂����A���̌��n������������邱�ƂȂ����s�P�\���Ԃ������Ƃ��́A���̊��Ԓ��x���������Ă������t���z�̑��z���x�����܂�(���{�s�ߑ�70���4��)�B
�@�Ȃ��A���s�P�\���Ԓ��̑ސE�N���҂����S���A�芼�ŋK�肷��⑰������ꍇ�́A���Y�̏ꍇ�Ɠ��l�A�⑰�N�����S�z�x������܂��B
�@���̏ꍇ�A���S�ɂ�获�s�P�\���Ԃ��������Ȃ����ƂƂȂ邽�߁A����܂Ő������Ă������z�ɂ��Ă̎x���͂���܂���B
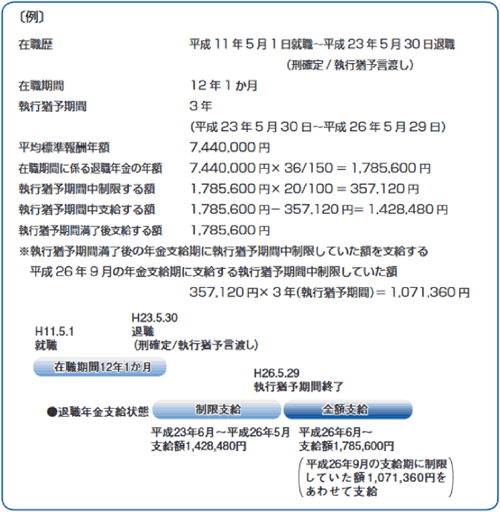
(3) �����ɂ��ސE�����ꍇ
�@�ݐE���ԂɌW��ސE�N���̔N�z�̂����A�����ɌW��C�����̌������ސE�N���̊�b�ƂȂ����ݐE���Ԃɐ�߂銄����100����20�̋��z���x���������܂�(���{�s�ߑ�70���1��)�B
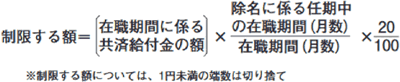
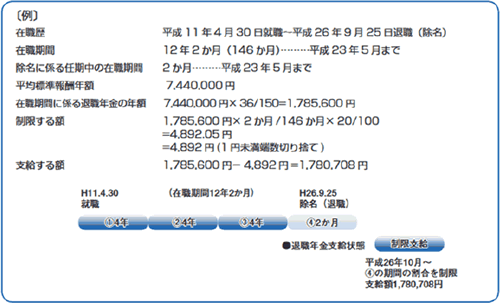
6�@���t���錠���̕ی�
�@���ϋ��t�����錠���́A����n���A�S�ۂɋ����A�܂��͍����������邱�Ƃ͂ł��܂���B
�@�������A�ސE�N�����錠�������ŁA�n���ł̑ؔ[�����ɂ�荷����������ꍇ�͉\�ł�(���@��167����3)�B
7�@�N���z�̉���
(1) �ďA�E�ɂ�����
�@�ސE�N����������Ăѓs���{���c��c���ɍďA�E���đސE�����ꍇ�́A�O��̍ݐE���Ԃ����Z���đސE�N���̔N�z�����肳��܂��B�������A���̉���z������O�̊z�������Ȃ��Ƃ��́A�]�O�̊z�Ƃ��܂�(���@��165���A�芼��31��)�B
(2) �����X���C�h����
�@�ސE�N���A�������a�N���y�ш⑰�N���̊z�́A�����X���C�h�ɂ����肪�s���܂��B�����X���C�h�ɂ��N���z�̉���Ƃ́A�N���̎����I�ȉ��l���ێ����邽�߂ɁA�����ȍ쐬�̑S������ҕ����w���̕ϓ��ɉ����Ď����I�ɍs������̂ł��B����Ώێ҂̕��ɂ́u�N���z����ʒm���v�̑��t�ɂ�肨�m�点���Ă��܂��B
8�@����
�@�N���ł��鋤�ϋ��t�����錠���ɂ́A�e�x���������ƂɈ����z�̎x�����錠��(�x����)�ƁA���̎x�����ݏo�����ƂɂȂ錠��(��{��)�Ƃ�����܂��B��҂̊�{���ɂ��ẮA���@��169���1���ɂ����āA���t���R��������������7�N�Ԑ������Ȃ������Ƃ��́A�����ɂ���ď��ł�����̂Ƃ���Ă��܂��B����A�O�҂̎x�����ɂ��ẮA5�N�Ԃ�����s��Ȃ����Ƃɂ���Ď����ŏ��ł��邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B
�@���̏��Ŏ������Ԃ̋N�Z���́A���@�̊��Ԍv�Z�̌����ɂ��A��{���ɂ��Ă͋��t���R����������(�����̌��萿�����ł��邱�ƂƂȂ�����)�̗����A�x�����ɂ��Ă͎x�������̗����̏����ƂȂ�܂�(�^�p���j��169���W)�B